蘇ったファイアストンの仲間達の誇り

もう一度、ファイアストンの仲間達のプライドを蘇らせるために
まずは、補強材技術戦略・開発部 補強材技術研究・戦略課に配属された宗川 彰毅さんからの質問です。

多くの従業員のトップというお立場で、人のやる気を奮い立たせるコツを教えてください。
石橋さん 難しい質問だ。役割や国籍・文化など、背景が違うチームメイトがたくさんいるから、その場の状況に応じてカスタマイズすることが大事だと思う。「相手に何が一番刺さるのかな?理解してもらえるかな?」ということを考えること。
また昔の話をするけれど、買収直後のファイアストンは、売り上げも落ちていて、従業員のモチベーションもとても下がっている状態だった。現場で使える予算も限られているし、チームワークで何とかしようという士気も乏しい。そこで問題の一つひとつの見える化を図り、解決をしようとした。会社の体制も変えて、商品のラインアップも、ブリヂストンの技術力を反映したモノに置き換えて、チャネル戦略も変えて、いろんなことを進めていった。最後まで課題として残ったのは、ファイアストンの従業員のプライド。彼らのプライドをどうやってもう一度蘇らせるか。その時に第6代社長の海﨑さんと相談したのが、もう一度「インディ500®」で戦うこと。米国で長い歴史があるモータースポーツレースで、1970年代にファイアストンの経営が傾いてから参戦できていなかった。これにもう一度トライしようと。インディアナポリス モーター スピードウェイ ミュージアムには歴代の優勝マシンがどーんと飾ってあって、1911年 第1回 優勝マシンをはじめ、多くのマシンにファイアストンのタイヤが着いている。「海﨑さん、これだよ!」と。
また当時はF1への参戦がブリヂストンで承認されていなかったんだけど、レーシングタイヤの技術開発自体はずっと続けていたからこういう提案ができた。ところが1993年に「インディ500」への参戦を対外発表すると、反対する小平の技術者の仲間もいた。九州出身の人が多いから、九州訛りで「なんでブリヂストンブランドでやらんと!?」って言う。海﨑さんと「ファイアストンが大変なんだ。皆で助けてくれ」って説得に回って、ようやく納得してくれた。また、石橋幹一郎さんも「ファイアストンを買ったということは、米国のブランドを預かったということ。ブリヂストンがもう一度彼らを蘇らせる必要がある」と言って、僕らを支持してくれた。
「インディ500」参戦の発表の後、ファイアストンのメンバーはとても喜んでくれた。「ブリヂストンは黒子に徹してファイアストンを復活させてくれるんだ!」と。これで皆のプライドが戻ってきた。そして、1996年には見事に優勝。業績自体も僕が想定していたよりも急速に回復した。これが僕のビジネス人生で目の当たりにした最大のモチベーションアップ。まるで映画の『ロッキー』の世界。主人公がフィラデルフィア図書館の前の階段を一気に駆け上がっていくような、そんな奇跡の復活だったと思っている。
また昔の話をするけれど、買収直後のファイアストンは、売り上げも落ちていて、従業員のモチベーションもとても下がっている状態だった。現場で使える予算も限られているし、チームワークで何とかしようという士気も乏しい。そこで問題の一つひとつの見える化を図り、解決をしようとした。会社の体制も変えて、商品のラインアップも、ブリヂストンの技術力を反映したモノに置き換えて、チャネル戦略も変えて、いろんなことを進めていった。最後まで課題として残ったのは、ファイアストンの従業員のプライド。彼らのプライドをどうやってもう一度蘇らせるか。その時に第6代社長の海﨑さんと相談したのが、もう一度「インディ500®」で戦うこと。米国で長い歴史があるモータースポーツレースで、1970年代にファイアストンの経営が傾いてから参戦できていなかった。これにもう一度トライしようと。インディアナポリス モーター スピードウェイ ミュージアムには歴代の優勝マシンがどーんと飾ってあって、1911年 第1回 優勝マシンをはじめ、多くのマシンにファイアストンのタイヤが着いている。「海﨑さん、これだよ!」と。
また当時はF1への参戦がブリヂストンで承認されていなかったんだけど、レーシングタイヤの技術開発自体はずっと続けていたからこういう提案ができた。ところが1993年に「インディ500」への参戦を対外発表すると、反対する小平の技術者の仲間もいた。九州出身の人が多いから、九州訛りで「なんでブリヂストンブランドでやらんと!?」って言う。海﨑さんと「ファイアストンが大変なんだ。皆で助けてくれ」って説得に回って、ようやく納得してくれた。また、石橋幹一郎さんも「ファイアストンを買ったということは、米国のブランドを預かったということ。ブリヂストンがもう一度彼らを蘇らせる必要がある」と言って、僕らを支持してくれた。
「インディ500」参戦の発表の後、ファイアストンのメンバーはとても喜んでくれた。「ブリヂストンは黒子に徹してファイアストンを復活させてくれるんだ!」と。これで皆のプライドが戻ってきた。そして、1996年には見事に優勝。業績自体も僕が想定していたよりも急速に回復した。これが僕のビジネス人生で目の当たりにした最大のモチベーションアップ。まるで映画の『ロッキー』の世界。主人公がフィラデルフィア図書館の前の階段を一気に駆け上がっていくような、そんな奇跡の復活だったと思っている。
人とモノの移動を止めないために ブリヂストンが進めるモビリティ社会への貢献
次は、デジタルツイン開発第2部 デジタルツイン開発第6課に配属された武田 颯さんからの質問です。

石橋さんがお考えになっている未来のモビリティ社会像を教えてください。
石橋さん モビリティ社会でもさまざまなソリューションが出てきている。そもそも人とモノが移動することが価値であって原点。かつて、メソポタミア文明で車輪が誕生したんだけど、これによって人とモノの移動がスムーズになって、文明が拡大していった。インドの国旗の真ん中にも「法輪」という仏教のシンボルがある。「法輪常転」って言って、この法輪が常に転がることで、仏の教えがどんどん広まって、皆が幸せになっていく。モビリティによって人間の想いが広まって、人々が交流して価値が生まれていくっていうのが今までの歴史なんだと、僕は思っている。
ブリヂストンは人とモノの動きをサステナブルにしていきたい。カーボンニュートラルももちろん大事。ただ、これだけじゃなくて、どうサステナブルにしていくか。EVや自動運転、カーシェアというのは、それぞれがソリューションの選択肢。カーシェアは稼働率の面で貢献できる。現在、実際に乗用車が動いて使われている時間はわずか5%程と言われている。残りの約95%の時間は駐車場で停まっているわけで、「資源生産性の観点ではどうなんだろう?」ということになる。だから、皆で自動車をシェアして、クルマ1台あたりの稼働率を上げていけば、経済合理性や資源生産性の向上につながっていく。自動運転については、例えば限界集落の高齢者は病院に行くのにも交通手段が無くて大変なケースがある。そこで、自動運転による車が、決まったルートを回って、高齢者を乗せて運んでいくようなこともテストされている。でも、自動運転のクルマに着いているタイヤがパンクしたら大変。運転手もいないわけだし。そこで、ブリヂストンの「AirFree®」が活躍できる。
こういうさまざまな取り組みを皆で積み重ねて、誰も置いてきぼりにしない、人とモノが移動する喜びを担保してくのは社会的な責任だし、ブリヂストンらしさを生かして貢献していきたい。例えば「Bridgestone E8 Commitment」の「Extension」にも「人とモノの移動を止めない」と書いてある。「地球は未来の子供たちからの預かり物」という思いが「Bridgestone E8 Commitment」には入っている。それぞれ意味のある8つの「E」で価値がつくれる。こういった価値を生んでいって、サステナビリティ、地球や企業の持続性が拡大していく。はっきりとした正解はないけど、こういう思いを皆で共有して、皆でやっていこうよということ。
車輪の話に戻ると、車輪の登場は人類・文明の歴史でも大きな一歩。これから人類が月に行っても、火星に行っても車輪は必要だし、ブリヂストンが取り組んでいるモビリティ社会への貢献は、人の想いの根源にもつながっていると思っている。それが僕の1つの誇りでもあるし、皆にもこういうことを意識して、どんどん挑戦していってほしい。
ブリヂストンは人とモノの動きをサステナブルにしていきたい。カーボンニュートラルももちろん大事。ただ、これだけじゃなくて、どうサステナブルにしていくか。EVや自動運転、カーシェアというのは、それぞれがソリューションの選択肢。カーシェアは稼働率の面で貢献できる。現在、実際に乗用車が動いて使われている時間はわずか5%程と言われている。残りの約95%の時間は駐車場で停まっているわけで、「資源生産性の観点ではどうなんだろう?」ということになる。だから、皆で自動車をシェアして、クルマ1台あたりの稼働率を上げていけば、経済合理性や資源生産性の向上につながっていく。自動運転については、例えば限界集落の高齢者は病院に行くのにも交通手段が無くて大変なケースがある。そこで、自動運転による車が、決まったルートを回って、高齢者を乗せて運んでいくようなこともテストされている。でも、自動運転のクルマに着いているタイヤがパンクしたら大変。運転手もいないわけだし。そこで、ブリヂストンの「AirFree®」が活躍できる。
こういうさまざまな取り組みを皆で積み重ねて、誰も置いてきぼりにしない、人とモノが移動する喜びを担保してくのは社会的な責任だし、ブリヂストンらしさを生かして貢献していきたい。例えば「Bridgestone E8 Commitment」の「Extension」にも「人とモノの移動を止めない」と書いてある。「地球は未来の子供たちからの預かり物」という思いが「Bridgestone E8 Commitment」には入っている。それぞれ意味のある8つの「E」で価値がつくれる。こういった価値を生んでいって、サステナビリティ、地球や企業の持続性が拡大していく。はっきりとした正解はないけど、こういう思いを皆で共有して、皆でやっていこうよということ。
車輪の話に戻ると、車輪の登場は人類・文明の歴史でも大きな一歩。これから人類が月に行っても、火星に行っても車輪は必要だし、ブリヂストンが取り組んでいるモビリティ社会への貢献は、人の想いの根源にもつながっていると思っている。それが僕の1つの誇りでもあるし、皆にもこういうことを意識して、どんどん挑戦していってほしい。
ファイアストンのリコール対応を通じて、感度を高めることの大切さを学ぶ
次は、G鉱山・産業・建設・航空タイヤ・ソリューション統括部門 企画部 販売企画課に配属された髙橋 宙太さんからの質問です。

石橋さんの、これまでの一番大きな失敗談と、それを乗り越えたエピソードを教えてください。
石橋さん 失敗だらけだったからなあ(笑)そのなかでも、最大の失敗はファイアストンのリコールの時かな。当時、自分はリプレイスの担当で、OEメーカーであるフォード社への対応をする立場ではなかった。リコールが発表されたとき、僕はスタッドレスタイヤ「BLIZZAK」についての説明会を、カナダのカルガリーにあるアイスリンクで行っていた。そんな中、急に電話がかかってきて、「大変なことになったから急いでワシントンに飛んでくれ」と。言われるままワシントンに飛んだんだけど、何が起きているか全くわからない。その後、2日間くらいかけて状況をキャッチアップして、対応をスタート。
このリコールで何を失敗したかというと、自分がリプレイスの担当だったから、OEメーカー向けの直需についてわからないことが多かった。ただ、もしもこの時、自分の感度がもっと高かったら、もっと早く状況を現場で理解して、早く対策も打てたんじゃないかと思う。その時は限られた関係者にしか共有されていない情報もあったんだけど、例えそうだったとしても、自分の感度を上げて、察知しなきゃダメだったなと。
その後は1年間、昼間はずっとアメリカのお客さんやマスコミ、フォード社への対応。一方で夜は日本との電話会議、睡眠時間も短くて、体がボロボロになった。会社を辞めていく人も多かったけど、そんな修羅場でも最後まで一緒に踏ん張ってくれた人たちもいたから、なんとか乗り越えられたかな。話を戻すと、当時の感度の鈍さが人生で一番の失敗だと思っている。
このリコールで何を失敗したかというと、自分がリプレイスの担当だったから、OEメーカー向けの直需についてわからないことが多かった。ただ、もしもこの時、自分の感度がもっと高かったら、もっと早く状況を現場で理解して、早く対策も打てたんじゃないかと思う。その時は限られた関係者にしか共有されていない情報もあったんだけど、例えそうだったとしても、自分の感度を上げて、察知しなきゃダメだったなと。
その後は1年間、昼間はずっとアメリカのお客さんやマスコミ、フォード社への対応。一方で夜は日本との電話会議、睡眠時間も短くて、体がボロボロになった。会社を辞めていく人も多かったけど、そんな修羅場でも最後まで一緒に踏ん張ってくれた人たちもいたから、なんとか乗り越えられたかな。話を戻すと、当時の感度の鈍さが人生で一番の失敗だと思っている。
バリューチェーン全体の最適化を目指して デジタル活用を進めていく
最後に、デジタルソリューションAI・IoT企画開発部門 デジタルAI・IoT企画課に配属された佐藤 拓海さんからの質問です。
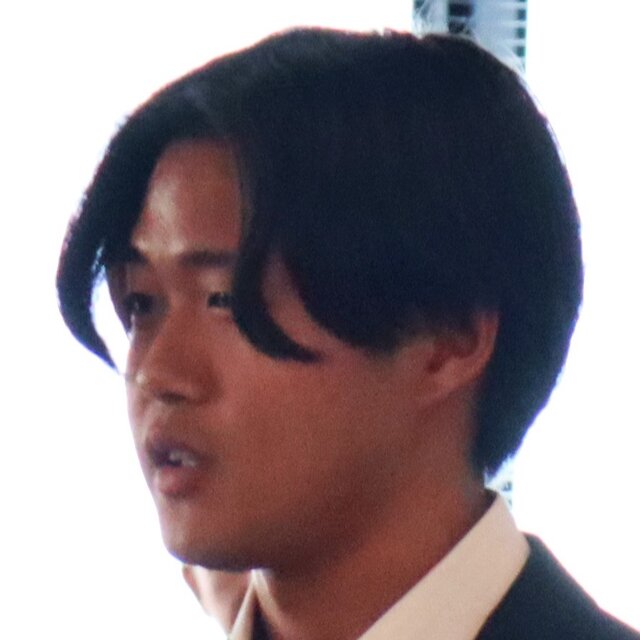
さまざまな会社でデジタル活用が進んでいますが、ブリヂストンがデジタル技術を活用して実現できることや、できたら面白いと思うことを教えてください。
石橋さん デジタル活用はまさに大きな経営課題。ブリヂストンはDX銘柄にも選ばれているけど、これからもこの分野にはもっと注力していかないといけないと思っている。一昔前はさまざまな仕事がトライアンドエラーの積み重ね。それに対して今はデジタル技術やAIを活用して、開発や設計など、さまざまな段階で正確なシミュレーションができるようになってきている。
生産段階においても、例えば彦根工場では全自動成型機「EXAMATION(エクサメーション)」というシステムがあるけれど、これによってさまざまなデータをリアルタイムで溜めつつ、生産の各工程をつなぐことができている。
次にお客様の使用段階。例えば鉱山の現場では、タイヤの故障で車両が止まってしまうと、それがダウンタイムになって、お客様が困ってしまう。そこでモニタリングシステム「Bridgestone iTrack」でタイヤのさまざまなデータをとりながら、ビジネスを止めないように故障の予兆管理や対策を行い、価値につなげている。特に航空機タイヤはこの分野では進んでいて、AIを活用した摩耗予測を行っている。基本的に航空機タイヤはリトレッドされて使われている。これまでは、いつタイヤの交換時期が来るか正確な予想が立てられないから、航空会社のスタッフは24時間体制で交換業務に備える必要があったし、タイヤの在庫もたくさん持っておく必要があった。そこで、JAL様と一緒にAIのアルゴリズムを活用した摩耗予測のソリューションを創りあげた。これによって、タイヤの交換がいつ必要になるかが精度高くわかる。人員やタイヤの在庫もこれに合わせて手配できるから、お客様の無駄な仕事・時間やコストが削減できて、JAL様とブリヂストンで、お互いにWin-Winになることができている。
こういう風に、開発からお客様の使用に至るまで、ブリヂストンの強い「リアル」と、「デジタル」を組み合わせて価値につなげている。また、皆も新入社員研修中に勉強してくれたとおり、ブリヂストンでもデジタル人財の育成を進めている。これからはバリューチェーンをどんどんつないでいかないといけない。バリューチェーン全体をダイナミックに最適化していくのが次に目指す形。モノの流れについても、モノづくり基盤技術「BCMA」で整理しようとしている。ブリヂストン全体の大きなモノの流れを再構築して、それをデジタル化・DX化して、会社全体を変えていきたい。まだまだ時間はかかると思う。だけど、新入社員の君達が中核になっていく頃にはそういう姿になっているようにしたい。これは本当に大変なこと。力を入れてやっていきたい。
生産段階においても、例えば彦根工場では全自動成型機「EXAMATION(エクサメーション)」というシステムがあるけれど、これによってさまざまなデータをリアルタイムで溜めつつ、生産の各工程をつなぐことができている。
次にお客様の使用段階。例えば鉱山の現場では、タイヤの故障で車両が止まってしまうと、それがダウンタイムになって、お客様が困ってしまう。そこでモニタリングシステム「Bridgestone iTrack」でタイヤのさまざまなデータをとりながら、ビジネスを止めないように故障の予兆管理や対策を行い、価値につなげている。特に航空機タイヤはこの分野では進んでいて、AIを活用した摩耗予測を行っている。基本的に航空機タイヤはリトレッドされて使われている。これまでは、いつタイヤの交換時期が来るか正確な予想が立てられないから、航空会社のスタッフは24時間体制で交換業務に備える必要があったし、タイヤの在庫もたくさん持っておく必要があった。そこで、JAL様と一緒にAIのアルゴリズムを活用した摩耗予測のソリューションを創りあげた。これによって、タイヤの交換がいつ必要になるかが精度高くわかる。人員やタイヤの在庫もこれに合わせて手配できるから、お客様の無駄な仕事・時間やコストが削減できて、JAL様とブリヂストンで、お互いにWin-Winになることができている。
こういう風に、開発からお客様の使用に至るまで、ブリヂストンの強い「リアル」と、「デジタル」を組み合わせて価値につなげている。また、皆も新入社員研修中に勉強してくれたとおり、ブリヂストンでもデジタル人財の育成を進めている。これからはバリューチェーンをどんどんつないでいかないといけない。バリューチェーン全体をダイナミックに最適化していくのが次に目指す形。モノの流れについても、モノづくり基盤技術「BCMA」で整理しようとしている。ブリヂストン全体の大きなモノの流れを再構築して、それをデジタル化・DX化して、会社全体を変えていきたい。まだまだ時間はかかると思う。だけど、新入社員の君達が中核になっていく頃にはそういう姿になっているようにしたい。これは本当に大変なこと。力を入れてやっていきたい。
Global CEOによる貴重なお話、新入社員の皆さんにとっては、長い研修の終わりに、大事なことをたくさん教わる機会になったのではないでしょうか。石橋さんのお言葉をしっかりと受け止め、配属先でも頑張っていきましょう!


※「コメントする」を押してもすぐにはコメントは反映されません。
管理者にて確認の上、反映されます。コメント掲載基準については こちら をご覧ください。
尚、投稿者につきましては、管理者でも特定できない仕様になっております。