モノづくりのナレッジやノウハウも「知財」!?
皆さんは「知的財産」(以下、知財)についてどれくらいご存じでしょうか?
ブリヂストンでは、知財の活用をサステナブルな成長のキードライバーの1つに位置づけています。バリューチェーン全体で生まれるさまざまな知財を可視化し、事業モデルに合わせて効果的に組み合わせながら活用することで、顧客価値と社会価値の向上に役立てています。また、ブリヂストンのこのような取り組みは、内閣総理大臣から「産業財産権制度普及発展特別功労企業 内閣総理大臣感謝状」を贈呈されるなど、社外からも注目を集めています。
前編では、知財の基本とブリヂストンの知財戦略について、知的財産部門長の荒木さんにお話を伺いました!
ブリヂストンでは、知財の活用をサステナブルな成長のキードライバーの1つに位置づけています。バリューチェーン全体で生まれるさまざまな知財を可視化し、事業モデルに合わせて効果的に組み合わせながら活用することで、顧客価値と社会価値の向上に役立てています。また、ブリヂストンのこのような取り組みは、内閣総理大臣から「産業財産権制度普及発展特別功労企業 内閣総理大臣感謝状」を贈呈されるなど、社外からも注目を集めています。
前編では、知財の基本とブリヂストンの知財戦略について、知的財産部門長の荒木さんにお話を伺いました!
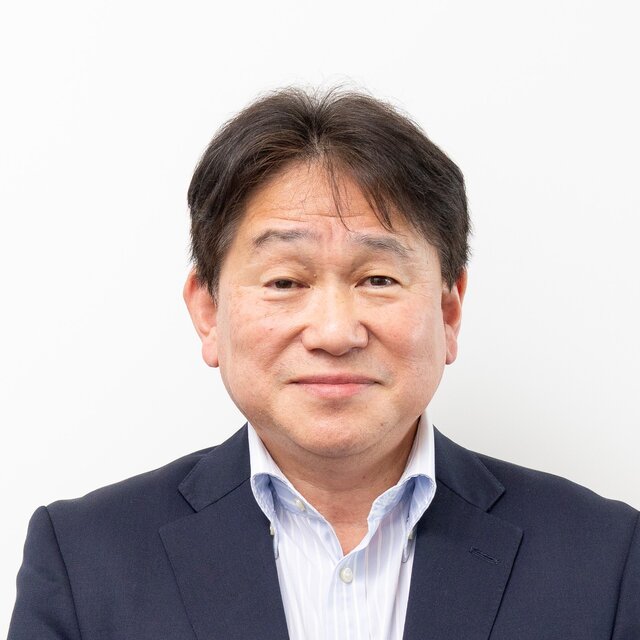
(株)ブリヂストン 知的財産部門長
荒木 充さん
1988年(株)ブリヂストン入社。入社以来約25年間タイヤの設計や開発企画に携わる。品質保証本部長を経て2016年1月より現職。
長年蓄積され、今も継ぎ足される「秘伝のタレ」
Arrow編集部 「知財」とは一体どのようなものなのでしょうか。
荒木さん 「知財」とは人のクリエイティブな活動から生まれた無形のアイデアなどで、「財産的な価値があるもの」です。知財と聞くと、「特許権」、「意匠権」、「商標権」などを思い浮かべる方が多いと思いますが、これらは「知的財産権」と呼ばれ、法律で規定された権利や法律上、保護される利益に係る権利のことを指します。
ですが、知財を形成するのはこれら権利化されたものだけではありません。私たちブリヂストンが90年以上にわたって築いてきたモノづくりのナレッジやノウハウ(知識・知見)、それを生み出す仕組みや風土、さらにはビッグデータなどの広義の知財によって「ブリヂストンの知財」は形成されています。
Arrow編集部 ナレッジやノウハウも知財に含まれるんですね。
荒木さん そうなんです。私たちが代々受け継ぎ発展させてきた経験や、可視化されていないナレッジやノウハウなども知財に含まれるんです。
例えばブリヂストンのスタッドレスタイヤは発泡ゴムが特徴ですが、発泡に関する基本特許は期限が切れてから20年以上が経過しており、言わば誰でもまねできる状態にあります。しかし、他社は同じやり方で追随してきません。きっと、同じように製造しても安定した品質と価格を実現できないからだと思います。そこにはつくり方をまねしただけでは再現できない、ブリヂストン独自のナレッジやノウハウがあります。発泡剤は条件によって発泡し過ぎることもあれば、全く発泡しないこともあり、コントロールするのが難しいものなんです。この発泡剤をコントロールする技術こそまさに「秘伝のタレ」であり、これこそが我々の強みだと考えています。
荒木さん 「知財」とは人のクリエイティブな活動から生まれた無形のアイデアなどで、「財産的な価値があるもの」です。知財と聞くと、「特許権」、「意匠権」、「商標権」などを思い浮かべる方が多いと思いますが、これらは「知的財産権」と呼ばれ、法律で規定された権利や法律上、保護される利益に係る権利のことを指します。
ですが、知財を形成するのはこれら権利化されたものだけではありません。私たちブリヂストンが90年以上にわたって築いてきたモノづくりのナレッジやノウハウ(知識・知見)、それを生み出す仕組みや風土、さらにはビッグデータなどの広義の知財によって「ブリヂストンの知財」は形成されています。
Arrow編集部 ナレッジやノウハウも知財に含まれるんですね。
荒木さん そうなんです。私たちが代々受け継ぎ発展させてきた経験や、可視化されていないナレッジやノウハウなども知財に含まれるんです。
例えばブリヂストンのスタッドレスタイヤは発泡ゴムが特徴ですが、発泡に関する基本特許は期限が切れてから20年以上が経過しており、言わば誰でもまねできる状態にあります。しかし、他社は同じやり方で追随してきません。きっと、同じように製造しても安定した品質と価格を実現できないからだと思います。そこにはつくり方をまねしただけでは再現できない、ブリヂストン独自のナレッジやノウハウがあります。発泡剤は条件によって発泡し過ぎることもあれば、全く発泡しないこともあり、コントロールするのが難しいものなんです。この発泡剤をコントロールする技術こそまさに「秘伝のタレ」であり、これこそが我々の強みだと考えています。
知財を価値に変える
Arrow編集部 受け継がれてきた「秘伝のタレ」をどのように活用されているのでしょうか。
荒木さん まずはどこにどのような「秘伝のタレ」があるのかを可視化することが重要です。
開発・設計、モノづくりの現場はもちろんのこと、調達などバリューチェーンの至る所に知財があります。業務中の何げないコミュニケーションひとつとっても、そこには多くの知財が秘められていて、どの現場でも毎日新たな知財が生まれています。
これまで可視化されずにナレッジ・ノウハウとして浸透してきた「秘伝のタレ」を見えるようにすることで、これまで意識していなかった強みを発見するきっかけになったり、知財の全体像をつかむことで次にやるべきことが明確になったり、可視化がもたらす影響は非常に多岐にわたります。さらに、知財が顧客価値・社会価値に変換される仕組みも可視化することで、競争力を高めるために必要な知財や有効な使い方などを、関連部署間でコミュニケーションすることができ、より効率的・戦略的な知財活用につながります。
事業モデルに合わせて知財を効果的に組み合わせながら活用することで、顧客価値と社会価値の向上に役立てる。これがブリヂストンの知財戦略です。
荒木さん まずはどこにどのような「秘伝のタレ」があるのかを可視化することが重要です。
開発・設計、モノづくりの現場はもちろんのこと、調達などバリューチェーンの至る所に知財があります。業務中の何げないコミュニケーションひとつとっても、そこには多くの知財が秘められていて、どの現場でも毎日新たな知財が生まれています。
これまで可視化されずにナレッジ・ノウハウとして浸透してきた「秘伝のタレ」を見えるようにすることで、これまで意識していなかった強みを発見するきっかけになったり、知財の全体像をつかむことで次にやるべきことが明確になったり、可視化がもたらす影響は非常に多岐にわたります。さらに、知財が顧客価値・社会価値に変換される仕組みも可視化することで、競争力を高めるために必要な知財や有効な使い方などを、関連部署間でコミュニケーションすることができ、より効率的・戦略的な知財活用につながります。
事業モデルに合わせて知財を効果的に組み合わせながら活用することで、顧客価値と社会価値の向上に役立てる。これがブリヂストンの知財戦略です。
巨額のライセンス費用に苦しんだ1960〜70年代
ラジアル化によってタイヤの構造が世界的に変革期を迎えていた当時、開発に遅れを取ったブリヂストンは、特許を持つ競合他社に多額のライセンス費用を払い、製造せざるを得ませんでした。その費用は、当時の年間開発費の多くを占めました。その経験から、80年代以降、多くの特許出願によってクロスライセンス※が可能となる特許力の強化が図られました。
その後、2010年代頃から他社対比の特許力と費用対効果を見極めながら量から質にシフトすることで実質的な競争力を高めています。
※特許権などの知的財産権を所有する会社同士が、互いに利用できるように契約を結ぶこと
その後、2010年代頃から他社対比の特許力と費用対効果を見極めながら量から質にシフトすることで実質的な競争力を高めています。
※特許権などの知的財産権を所有する会社同士が、互いに利用できるように契約を結ぶこと
Arrow編集部 目に見えない知財であるナレッジやノウハウをどのように可視化するのでしょうか。
荒木さん 開発現場や事業現場などバリューチェーン全ての現場に対して、知財部門のメンバーが日常的に寄り添ったコミュニケーションを行うことで可視化に取り組んでいます。特許化の相談だけでなく、どんな知財を持っているのかを聞き取る草の根活動を中心に行うことで、これまでどんな苦労をして課題を乗り越えたのか、そこでどんなナレッジやノウハウが生まれて使われたのかを理解・抽出することが可視化の第一歩となります。
そうして創出された知財がどのように価値に変換されてきたのか、そのプロセスや仕組みを「インフルエンスダイアグラム」として可視化しています。
荒木さん 開発現場や事業現場などバリューチェーン全ての現場に対して、知財部門のメンバーが日常的に寄り添ったコミュニケーションを行うことで可視化に取り組んでいます。特許化の相談だけでなく、どんな知財を持っているのかを聞き取る草の根活動を中心に行うことで、これまでどんな苦労をして課題を乗り越えたのか、そこでどんなナレッジやノウハウが生まれて使われたのかを理解・抽出することが可視化の第一歩となります。
そうして創出された知財がどのように価値に変換されてきたのか、そのプロセスや仕組みを「インフルエンスダイアグラム」として可視化しています。
(株)ブリヂストン 知的財産部門のメンバーたち
知的財産部門は現在60余名。そのうち知的財産権の専門家である弁理士の資格を持っているメンバーは10名程ですが、他のメンバーも、弁理士に匹敵する知的財産の全般的な知識と技能を有しています。それぞれがブリヂストンの各現場の業務について精通していることで、競合や業界の知財動向にも気を配りつつ、バリューチェーン全ての現場の皆さんと日々密なコミュケーションを取ることができます。開発・設計や生産、販売などの現場でどのような苦労をして課題を乗り越えたか、そこでどんな知財が生まれて使われたのかを理解・抽出し、可視化に取り組んでいます。
次回後編では、可視化された「秘伝のタレ」をどのように価値に変更しているのか、知財を効果的に組み合わせる「知財ミックス」戦略について伺います。






※「コメントする」を押してもすぐにはコメントは反映されません。
管理者にて確認の上、反映されます。コメント掲載基準については こちら をご覧ください。
尚、投稿者につきましては、管理者でも特定できない仕様になっております。